AIAN BLOG
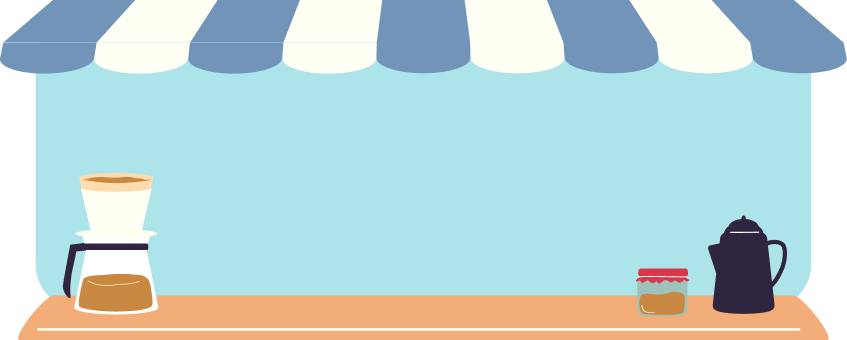

この記事を書いている人

あいあんクック社長 竹内 晋
平成3年創業、キッチンカーのパイオニアあいあんクック(AIAN COOK)社長
創業以来これまで1000台超えるキッチンカーを手掛けてきた竹内。
キッチンカーの制作販売だけでなく自らのたこ焼きのキッチンカーで得た経営のノウハウを活かし、多くのキッチンカーオーナーの開業支援も行ってきました。
決して甘くないキッチンカーの独立開業に役立つ情報を、少し厳しい言葉もありつつ愛をもって、
これからキッチンカーでの開業を考えている方、既にキッチンカーを営業されている方のお役に立てる情報を発信していきます。
キッチンカー開業の夢を叶えるための第一歩、営業許可の取得方法を徹底解説!この記事では、保健所での申請手順を図解付きで分かりやすく説明し、必要書類や設備要件、費用、よくある質問まで網羅しています。2025年最新の情報に基づき、HACCPに基づいた衛生管理についても詳しく解説。東京都、大阪市、名古屋市の保健所一覧も掲載しているので、あなたの開業準備を強力にサポートします。この記事を読めば、スムーズに営業許可を取得し、キッチンカービジネスを成功させるための道筋が明確になります。
キッチンカーで飲食店営業を始めたいけれど、営業許可の取得って難しそう…と感じている方もいるかもしれません。この章では、キッチンカー営業許可の基礎知識について、分かりやすく解説します。
キッチンカー営業許可とは、移動販売形態の飲食店営業を行う際に必要な許可です。保健所から交付され、食品衛生法に基づいて、安全な食品を提供するための基準を満たしていることを証明するものです。無許可で営業すると罰則の対象となるため、必ず取得しなければなりません。
キッチンカーは、調理から提供までを限られたスペースで行うため、食中毒のリスクが高まる可能性があります。そのため、食中毒を予防し、消費者の安全を守るために、保健所の許可が必要となります。保健所は、キッチンカーの設備や衛生管理状況を検査し、基準を満たしていることを確認した上で許可を交付します。
許可を受けることで、お客様は安心してキッチンカーを利用することができます。また、事業者側も、安全な食品を提供しているという信頼を得ることができ、ビジネスの成功にも繋がります。
キッチンカーで取得できる営業許可は主に「飲食店営業許可」です。ただし、提供する食品の種類によっては、他の許可が必要になる場合もあります。
| 許可の種類 | 内容 | 対象となる食品 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 調理した食品を提供する営業 | 弁当、ハンバーガー、カレーライス、クレープ、たこ焼きなど |
| 菓子製造業許可 | 菓子を製造して販売する営業 | ケーキ、焼き菓子、和菓子など |
| アイスクリーム類製造業許可 | アイスクリーム類を製造して販売する営業 | アイスクリーム、ソフトクリーム、アイスキャンディーなど |
| 乳処理業許可 | 牛乳などを処理して販売する営業 | 牛乳、乳飲料など |
提供する食品によって必要な許可が異なるため、事前に保健所に確認することが重要です。例えば、アイスクリームを製造・販売する場合は、「アイスクリーム類製造業許可」が必要になります。また、複数の種類の食品を扱う場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。
詳しくは東京都福祉保健局のウェブサイトなどを参考にしてください。
キッチンカーで営業するためには、食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。許可を得るためには、保健所が定める設備要件と衛生管理基準を満たす必要があります。この章では、キッチンカー営業許可に必要な設備と要件について詳しく解説します。
キッチンカーの車両には、食品衛生法で定められた以下の設備が必要です。これらの設備が適切に設置され、機能していることが許可取得の必須条件となります。
清潔な給水設備と排水設備は、食品衛生上非常に重要です。十分な容量の給水タンクと排水タンクを設置し、それぞれのタンクに適切な排水口を設ける必要があります。また、給水タンクへの給水方法も明確にしておく必要があります。シンクは、温水を供給できる設備を備え、手洗い専用のシンクを設けることが望ましいです。材料や器具の洗浄には、専用のシンクを用意し、二槽式または三槽式のシンクが推奨されます。東京都福祉保健局 キッチンカー等の営業許可
提供する食品の種類に応じて、適切な調理設備が必要です。例えば、揚げ物を行う場合はフライヤー、焼きそばを作る場合は鉄板など、必要な設備を備え付ける必要があります。また、火を使う場合は換気設備も必要です。さらに、調理台は清潔で、適切な材質(例えば、ステンレスなど)でなければなりません。厚生労働省 食品衛生の窓
食材の鮮度を保つためには、適切な冷蔵・冷凍設備が不可欠です。提供する食品の種類や量に応じて、適切な容量の冷蔵庫や冷凍庫を設置する必要があります。また、温度計を設置し、庫内温度を適切に管理することが重要です。日本冷凍空調設備工業連合会
キッチンカーで営業するには、食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。食品衛生責任者は、食品衛生に関する知識を持ち、営業所の衛生管理を行う責任者です。資格取得には、都道府県が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。東京都福祉保健局 食品衛生責任者養成講習会
HACCP(ハサップ)とは、食品の製造・加工工程における危害要因を特定し、その危害を防止するための重要管理点を継続的に監視・記録することで、食品の安全性を確保する衛生管理手法です。キッチンカー営業においても、HACCPに沿った衛生管理が求められます。具体的には、食材の仕入れから調理、提供までの各工程における危害要因を分析し、適切な管理手順を確立する必要があります。厚生労働省 HACCP
HACCPに基づく衛生管理に加えて、日々の衛生管理も重要です。以下の項目について、毎日点検を行い、記録を残すようにしましょう。
| 項目 | 点検内容 |
|---|---|
| 施設 | 清掃状況、整理整頓、害虫の発生状況 |
| 設備 | 給排水設備の動作確認、冷蔵・冷凍庫の温度確認、調理器具の洗浄状況 |
| 食品 | 食材の保管状況、賞味期限・消費期限の確認 |
| 従事者 | 健康状態、衛生的な服装、手洗い |
食中毒などの緊急事態が発生した場合に備えて、対応マニュアルを作成しておくことが重要です。マニュアルには、連絡体制、原因究明の方法、再発防止策などを記載しておきましょう。また、保健所への連絡方法も確認しておきましょう。消費者庁 食中毒
キッチンカー営業許可を取得するには、保健所への申請が必須です。ここでは、その手順をステップごとに詳しく解説します。図解を交えて分かりやすく説明するので、ぜひ参考にしてください。
まずは、保健所に提出する必要書類を準備しましょう。主な必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書 | 所定の様式に必要事項を記入 | 保健所で入手可能 |
| 施設概要書 | キッチンカーの設備や構造に関する情報 | 図面なども必要 |
| 食品衛生責任者資格証の写し | 食品衛生責任者の資格を証明する書類 | 有効期限内に限る |
| 営業設備に関する図面 | キッチンカーの平面図、側面図、設備配置図など | 寸法を明記 |
| 給排水設備に関する図面 | 給水設備、排水設備の図面 | 詳細な情報を記載 |
| メニュー表 | 提供する料理や飲み物のリスト | 価格も記載 |
必要書類は各自治体の保健所によって異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。 各保健所のウェブサイトで確認できる場合もありますし、電話で問い合わせることも可能です。不明な点は、遠慮なく保健所に相談しましょう。
申請書の書き方や必要書類の詳細については、東京都福祉保健局のウェブサイトなどを参考にしてください。
必要書類が揃ったら、管轄の保健所に申請します。申請前に、保健所に相談に行くことを強くおすすめします。 事前に相談することで、必要書類の確認や不明点の解消ができます。スムーズな申請につながるだけでなく、許可取得までの時間を短縮できる可能性もあります。
保健所での相談は、電話または窓口で行うことができます。相談時には、キッチンカーの営業内容や設備について詳しく説明しましょう。図面や写真などを持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。
保健所へ申請書類を提出後、保健所の担当者による施設検査が行われます。施設検査では、キッチンカーの設備が食品衛生法の基準を満たしているかを確認されます。
検査項目は、給排水設備、調理設備、冷蔵・冷凍設備、衛生管理体制など多岐にわたります。事前に、食品衛生法に基づく営業許可基準を確認し、必要な設備を整えておきましょう。 また、HACCPに基づいた衛生管理計画書も重要です。検査時に担当者から質問される場合もあるので、内容を理解しておきましょう。
施設検査に合格すると、営業許可証が交付されます。営業許可証は、キッチンカー内で常に掲示する必要があります。
許可証の交付には、数週間から数ヶ月かかる場合があります。開業予定日までに余裕を持って申請手続きを行いましょう。また、許可証の有効期限は、交付日から1年間または数年間です。更新手続きが必要となるため、期限切れにならないように注意しましょう。
これらのステップを踏むことで、キッチンカーの営業許可を取得することができます。申請手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧に進めていけば大丈夫です。不明な点は、積極的に保健所に相談しましょう。
キッチンカー営業許可の申請に関してよくある質問をまとめました。申請前に疑問を解消し、スムーズな手続きを進めましょう。
キッチンカー営業許可申請の費用は、都道府県によって異なりますが、概ね1万円から2万円程度です。手数料は、申請時に納付します。具体的な金額は、各都道府県の保健所に確認してください。
参考:厚生労働省 食品衛生関係営業許可申請等の手数料
キッチンカー営業許可申請に必要な期間は、1ヶ月から2ヶ月程度です。これは、保健所による審査や施設検査の期間を含みます。繁忙期にはさらに時間がかかる場合があるので、余裕を持って申請しましょう。また、書類に不備があると、審査に時間がかかることがあるので、正確に記入することが重要です。
保健所への相談は、電話、メール、窓口訪問のいずれかの方法で行います。事前に予約が必要な場合もあるので、各保健所のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせてください。相談内容は、申請手続き、必要書類、設備要件など、多岐にわたります。疑問点を明確にして相談することで、スムーズな申請につながります。
不明点があれば、遠慮なく保健所に相談しましょう。
キッチンカーで営業する場合、主に「移動販売営業許可」を取得します。これは、食品衛生法に基づく許可で、都道府県知事または保健所設置市の市長が発行します。飲食店営業許可とは異なり、営業場所が固定されていない点が特徴です。また、提供する食品の種類によって、許可の範囲が異なります。例えば、弁当やパンの販売のみであれば、比較的簡易な手続きで許可を取得できますが、調理を伴う場合は、より厳格な設備基準を満たす必要があります。
キッチンカー営業には、食品衛生責任者の選任が必須です。食品衛生責任者は、営業許可の申請者本人でも、従業員でも構いません。食品衛生責任者の資格は、都道府県が実施する講習会を受講することで取得できます。講習会の内容は、食品衛生法、食品の衛生管理、食中毒の予防などです。有効期限はないため、一度取得すれば更新の必要はありません。
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品の安全性を確保するための衛生管理手法です。キッチンカー営業においても、HACCPに沿った衛生管理が求められます。具体的には、危害要因分析、重要管理点の特定、モニタリング、改善措置などの手順を踏まえ、衛生管理計画を作成し、実施する必要があります。保健所では、HACCPに基づいた衛生管理計画の作成について、相談や指導を行っています。
キッチンカーの設備要件は、提供する食品の種類や調理方法によって異なります。一般的な設備要件としては、給排水設備、調理設備、冷蔵・冷凍設備などがあります。給排水設備は、清潔な水を供給し、汚水を適切に処理できるものでなければなりません。調理設備は、食品を安全に調理できるもので、火を使う場合は、消火設備も必要です。冷蔵・冷凍設備は、食品を適切な温度で保存できるものでなければなりません。保健所は、これらの設備が基準を満たしているか、施設検査で確認します。
| 設備 | 要件 |
|---|---|
| 給排水設備 | 清潔な給水設備と、排水設備を備えていること。排水設備は、適切な処理能力を有すること。 |
| 調理設備 | 食品の種類に応じた適切な設備を備えていること。火気を使用する場合は、消火設備も設置すること。 |
| 冷蔵・冷凍設備 | 食品を適切な温度で保存できる能力を有すること。温度計を設置し、定期的に温度管理を行うこと。 |
| 洗浄設備 | 食器や調理器具を洗浄・殺菌できる設備を備えていること。洗剤や消毒液を適切に使用すること。 |
| 換気設備 | 調理による煙や臭気を排出できる設備を備えていること。 |
営業許可を取得した後も、営業開始届の提出や、定期的な検査など、必要な手続きがあります。営業開始届は、営業開始の7日前までに保健所に提出します。定期的な検査は、保健所が実施し、食品衛生法の遵守状況を確認します。また、食品衛生責任者の変更や、営業内容の変更などがあった場合も、保健所に届け出る必要があります。
営業許可を取得したら、いよいよキッチンカーでの営業開始です。しかし、許可を取得しただけで終わりではありません。その後も様々な手続きや衛生管理、法令遵守が求められます。スムーズに事業を継続していくために、許可取得後の注意点を確認しておきましょう。
保健所から営業許可証を受け取ったら、営業開始前に営業開始届を保健所に提出する必要があります。これは、実際に営業を開始する日付を保健所に伝えるための手続きです。許可証を受け取ってから10日以内に提出するのが一般的です。提出期限は保健所によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。また、営業開始届と同時に、食品衛生責任者の氏名や資格の種類、営業設備の概要などの変更届が必要となるケースもあります。詳しくは東京都福祉保健局のウェブサイトなどを参考にしてください。
キッチンカー営業において、食品衛生管理は最も重要な要素です。食中毒などを発生させれば、事業の存続に関わるだけでなく、お客様の健康にも重大な影響を与えます。常に衛生管理を徹底し、安全な食品を提供するよう心がけましょう。
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品の製造・加工工程における危害を分析し、その危害を防止するための重要管理点を継続的に監視・記録する衛生管理手法です。キッチンカー営業においても、HACCPに基づいた衛生管理計画を作成し、実施することが重要です。厚生労働省のウェブサイトでは、HACCPに関する情報が提供されています。
日々の衛生管理状況を記録し、適切に保管することも重要です。記録すべき項目としては、食材の入荷日・消費期限、調理温度、洗浄・消毒記録などが挙げられます。これらの記録は、万が一食中毒が発生した場合の原因究明や再発防止に役立ちます。
従業員への衛生教育も欠かせません。適切な手洗いや消毒方法、食品の取り扱い方法などを定期的に教育し、衛生意識の向上を図る必要があります。
営業許可を取得した後も、保健所による定期的な検査が行われます。検査では、施設の衛生状態や食品の保存状況などがチェックされます。検査結果によっては、改善指導を受ける場合もあるので、常に衛生管理を徹底しておくことが重要です。また、車両の定期点検や整備も忘れずに行い、安全な営業を心がけましょう。
定期検査では、主に以下の項目がチェックされます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設の衛生状態 | 調理場の清潔さ、器具の洗浄・消毒状況、ゴミの処理状況など |
| 食品の保存状況 | 食材の保管温度、消費期限の管理、表示の有無など |
| 衛生管理記録 | HACCPに基づいた記録の有無、記録内容の正確さなど |
| 従業員の衛生状態 | 手洗い・消毒の徹底、清潔な服装など |
検査の結果、衛生状態に問題がある場合は、保健所から改善指導を受けることがあります。指導内容に従って速やかに改善を行い、再検査を受ける必要があります。改善が不十分な場合は、営業許可の取り消しとなる可能性もあるので、注意が必要です。
その他にも、食品表示法に基づいた食品表示の徹底や、道路交通法の遵守、消防法関連の規定遵守なども必要です。営業許可を取得したからといって安心するのではなく、関連法規を常に確認し、法令遵守を徹底することが重要です。また、各自治体によっては、独自の条例を設けている場合もあります。事前に確認しておきましょう。
キッチンカー開業には、車両の購入費や設備投資、各種申請費用、そして継続的なランニングコストなど、様々な費用が発生します。開業前にしっかりと資金計画を立て、余裕を持った予算を確保することが重要です。初期費用とランニングコストに分けて詳しく解説します。
初期費用は、キッチンカー開業までに必要となる費用のことです。主な内訳は以下の通りです。
キッチンカーの車両費用は、新車か中古車か、車両のサイズや種類、装備によって大きく異なります。軽自動車ベースのキッチンカーであれば150万円〜300万円程度、普通トラックベースの大型キッチンカーでは500万円〜1000万円以上となる場合もあります。中古車の場合は数百万円程度から購入できる場合もありますが、車両の状態をよく確認することが重要です。また、既存の車両を改造する場合、改造費用が別途発生します。
車両購入費用を抑える方法としては、中古車を選ぶ、リース契約を利用する、軽トラックをベースにDIYで改造するなどがあります。ただし、DIYで改造する場合は、保健所の基準を満たす必要があるため、事前に確認が必要です。
キッチンカーの設備費用は、提供するメニューや車両のサイズによって異なります。厨房機器、冷蔵庫、冷凍庫、給排水設備、発電機など、必要な設備をリストアップし、それぞれに見積もりを取りましょう。50万円〜150万円程度が目安となります。
| 設備 | 費用目安 |
|---|---|
| 厨房機器(コンロ、オーブン、フライヤーなど) | 20万円〜50万円 |
| 冷蔵庫/冷凍庫 | 10万円〜30万円 |
| 給排水設備 | 5万円〜15万円 |
| 発電機 | 5万円〜15万円 |
| その他(調理器具、食器、備品など) | 5万円〜10万円 |
キッチンカーの営業許可申請には、数千円〜数万円程度の費用がかかります。都道府県によって費用が異なるため、事前に確認しておきましょう。また、食品衛生責任者資格の取得費用も必要です。講習会の受講費用は1万円前後です。
ランニングコストは、キッチンカー営業を継続していく上で毎月発生する費用のことです。主な内訳は以下の通りです。
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 食材費 | 売上の30%〜40% |
| 燃料費(ガソリン、LPガスなど) | 1万円〜3万円 |
| 車両維持費(車検、修理、保険など) | 1万円〜2万円 |
| 水道光熱費 | 1万円〜2万円 |
| 駐車場代 | 1万円〜3万円 |
| 販売場所使用料 | イベント出店の場合、数千円〜数万円 |
| 消耗品費(包装資材、洗剤など) | 5千円〜1万円 |
ランニングコストは、売上や営業日数、販売場所などによって変動します。開業前にしっかりと試算し、黒字化できる見込みを立てておくことが重要です。損益分岐点を把握し、売上目標を設定することで、スムーズな経営につながります。
より詳しい情報については、経済産業省のキッチンカー開業ガイドも参考にしてください。
東京都内には、複数の保健所が存在し、キッチンカーの営業許可申請を行う保健所は、営業場所の地域を管轄する保健所になります。申請先を間違えないように注意しましょう。以下に東京都の保健所一覧を掲載します。各保健所の管轄区域、住所、電話番号、ウェブサイトへのリンクを記載していますので、ご自身の営業区域に基づいて適切な保健所を選択してください。
保健所への問い合わせは、申請前に事前に行うことを強く推奨します。 各保健所によって必要書類や手続きが若干異なる場合があるため、疑問点を解消し、スムーズな申請を行うために、事前に電話またはウェブサイトで確認しておきましょう。
| 保健所名 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| 千代田保健所 | 千代田区 | 千代田区九段南1-2-1 | 03-3234-0123 | 千代田保健所ウェブサイト |
| 中央保健所 | 中央区 | 中央区築地1-1-1 | 03-3541-5931 | 中央保健所ウェブサイト |
| 港保健所 | 港区 | 港区芝5-33-10 | 03-3456-3101 | 港保健所ウェブサイト |
| 新宿保健所 | 新宿区 | 新宿区歌舞伎町2-44-1 | 03-5273-3831 | 新宿保健所ウェブサイト |
| 文京保健所 | 文京区 | 文京区春日1-16-21 | 03-3812-1151 | 文京保健所ウェブサイト |
| 台東保健所 | 台東区 | 台東区東上野4-20-6 | 03-3847-9161 | 台東保健所ウェブサイト |
| 墨田保健所 | 墨田区 | 墨田区吾妻橋3-15-1 | 03-5608-6901 | 墨田保健所ウェブサイト |
上記は主要な保健所の一部です。東京都には23区以外にも市町村があり、それぞれに保健所が設置されている場合があります。自身の営業区域を管轄する保健所を必ず確認してください。 東京都福祉保健局 保健所一覧から、詳細な情報を確認できます。
東京都内でのキッチンカー営業は、他の地域と比べて競争が激しく、許可取得の難易度も高いと言われています。そのため、事前の準備と情報収集が非常に重要です。
必須ではありませんが、強く推奨されています。 事前に相談することで、必要書類や手続きに関する疑問を解消し、スムーズな申請につながります。
東京都では、食品衛生法に基づく一般的な規制に加え、道路交通法や都市公園法などの関連法規にも注意が必要です。路上駐車の禁止区域や公園内での営業許可など、事前に確認しておきましょう。
私有地での営業の場合は、土地所有者の許可が必要です。公共の場所での営業は、道路使用許可や公園使用許可など、それぞれの場所を管理する機関への申請が必要です。詳しくは各区市町村の担当部署に問い合わせてください。
東京都内でのキッチンカー営業は、適切な許可取得と法令遵守が不可欠です。上記の情報と合わせて、厚生労働省の食品衛生関係情報なども参考に、安全で安心な営業を心がけてください。
大阪市では、保健所業務を区役所が担っています。各区の担当窓口で、キッチンカー営業許可に関する相談や申請手続きを行います。大阪市でキッチンカー営業を始める方は、営業予定区域を担当する区役所に問い合わせましょう。
大阪市内の区役所一覧と、主な担当窓口、電話番号、所在地をまとめました。 営業区域を担当する区役所へ、事前に電話で問い合わせてから訪問することをおすすめします。
| 区名 | 担当窓口 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6313-9969 | 大阪市北区扇町1-1-27 |
| 都島区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6929-9555 | 大阪市都島区中野町4-15-51 |
| 福島区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6464-9967 | 大阪市福島区鷺洲5-12-4 |
| 此花区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6460-9901 | 大阪市此花区春日出北1-6-1 |
| 中央区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6267-9922 | 大阪市中央区大手前1-2-17 |
| 西区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6532-9922 | 大阪市西区新町4-5-14 |
| 港区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6571-9982 | 大阪市港区市岡1-1-17 |
| 大正区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6552-9942 | 大阪市大正区小林東1-28-19 |
| 天王寺区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6774-9952 | 大阪市天王寺区真田山町1-2 |
| 浪速区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6632-9922 | 大阪市浪速区難波中3-8-9 |
| 西淀川区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6478-9977 | 大阪市西淀川区千舟1-1-1 |
| 淀川区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6308-9978 | 大阪市淀川区新北野1-9-5 |
| 東淀川区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6322-9977 | 大阪市東淀川区豊新2-1-4 |
| 東成区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6972-0001 | 大阪市東成区大今里西3-2-17 |
| 生野区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6715-9961 | 大阪市生野区勝山南3-1-19 |
| 旭区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6955-9982 | 大阪市旭区中宮4-16-18 |
| 城東区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6939-1322 | 大阪市城東区中央3-5-45 |
| 鶴見区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6915-9942 | 大阪市鶴見区横堤1-1-40 |
| 阿倍野区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6622-9969 | 大阪市阿倍野区文の里1-1-1 |
| 住之江区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6682-9941 | 大阪市住之江区南港北1-14-16 |
| 住吉区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6694-9978 | 大阪市住吉区南住吉3-15-55 |
| 東住吉区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6702-9941 | 大阪市東住吉区北田辺5-1-15 |
| 平野区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6791-9982 | 大阪市平野区背戸口3-8-19 |
| 西成区 | 保健福祉センター 生活衛生課 | 06-6659-9953 | 大阪市西成区花園北2-1-17 |
各区役所の詳細情報については、大阪市の公式ウェブサイトをご確認ください。
保健所への問い合わせは、営業時間内に電話で行うのが確実です。 ホームページで営業時間や担当部署を確認してから問い合わせましょう。
名古屋市でキッチンカー営業許可を取得するには、各区の保健所が窓口となります。管轄区域によって担当保健所が異なるため、営業予定地を管轄する保健所を確認しましょう。
名古屋市では、保健所ではなく「衛生事務所」という名称が用いられています。
| 区名 | 衛生事務所名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 千種区 | 千種保健センター | 名古屋市千種区千種二丁目10番20号 | 052-763-1881 |
| 東区 | 東保健センター | 名古屋市東区葵一丁目27番22号 | 052-935-2551 |
| 北区 | 北保健センター | 名古屋市北区大曽根三丁目14番45号 | 052-911-2781 |
| 西区 | 西保健センター | 名古屋市西区城西四丁目27番2号 | 052-531-3511 |
| 中村区 | 中村保健センター | 名古屋市中村区太閤通五丁目1番1号 | 052-453-2111 |
| 中区 | 中保健センター | 名古屋市中区栄四丁目1番8号 | 052-253-6111 |
| 昭和区 | 昭和保健センター | 名古屋市昭和区滝川町41番地 | 052-842-2211 |
| 瑞穂区 | 瑞穂保健センター | 名古屋市瑞穂区瑞穂通八丁目25番地 | 052-852-2551 |
| 熱田区 | 熱田保健センター | 名古屋市熱田区旗屋一丁目11番31号 | 052-681-4121 |
| 中川区 | 中川保健センター | 名古屋市中川区尾頭橋三丁目4番10号 | 052-361-4111 |
| 港区 | 港保健センター | 名古屋市港区港明一丁目10番27号 | 052-652-1151 |
| 南区 | 南保健センター | 名古屋市南区三吉町一丁目1番地 | 052-611-4161 |
| 守山区 | 守山保健センター | 名古屋市守山区小幡南一丁目1番10号 | 052-796-1251 |
| 緑区 | 緑保健センター | 名古屋市緑区鳴海町字山下32番地の1 | 052-899-2111 |
| 名東区 | 名東保健センター | 名古屋市名東区一社二丁目85番地 | 052-772-1151 |
| 天白区 | 天白保健センター | 名古屋市天白区植田南二丁目1101番地 | 052-801-2881 |
営業場所によって、連絡先が変わる可能性があります。必ず事前に、名古屋市のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
各衛生事務所の管轄区域は、原則として区の境界線に従います。しかし、一部例外もあるため、名古屋市のウェブサイトで詳細を確認することをおすすめします。
各衛生事務所には、電話や窓口で相談することができます。訪問相談の場合は、事前に予約が必要な場合もありますので、各衛生事務所に問い合わせてください。
申請時には、必要書類を揃えて、管轄の衛生事務所に提出します。必要書類や申請手続きは、変更される場合もありますので、最新の情報を確認しましょう。 また、施設検査が行われるため、事前に車両や設備を整えておく必要があります。
この記事では、キッチンカー営業許可の取得方法について、保健所での申請手順を中心に詳しく解説しました。許可取得には、車両の設備要件や食品衛生責任者の資格、HACCPに基づいた衛生管理体制の構築など、様々な要件を満たす必要があります。申請手順は、必要書類の準備、保健所への申請と相談、施設検査、そして営業許可証の交付という流れになります。申請前に保健所に相談することで、スムーズな許可取得につながります。許可取得後も、営業開始届の提出や衛生管理の徹底、定期的な検査など、継続的な取り組みが必要です。キッチンカー開業を成功させるためには、事前の準備と情報収集が不可欠です。この記事が、これからキッチンカー事業を始めようとする方の参考になれば幸いです。
移動販売車やキッチンカーに始めるにあたって、
一番大切な開業相談は代表竹内晋がみずからおこなっております。
竹内は、みずからもたこ焼きの移動販売でキッチンカーを始め、
さまざまなキッチンカーを育ててきました。
具体的な開業内容が決まっている方も、まだまだ構想段階の方も、
開業相談にぜひいらしてください。
また、「体験会に参加したい」という方もご相談ください。
体験会では実際のキッチンカーで調理をおこない、
接客なども体験することができます。
個人開業相談と体験会参加をぜひお問い合わせください
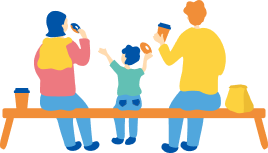
〒190-0002
東京都立川市幸町2-26-1
TEL :042-535-3455
FAX: 042-535-6455
営業時間:10時~18時(火曜日~土曜日)
画像をクリックで拡大します